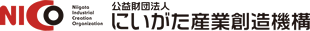生産管理の役割を再認識。
利益を生む管理体制へ変化するために製造部と営業部が連携し体制を強化
植物性乳酸菌の専門メーカーであるバイオテックジャパンは、新潟県よろず支援拠点を活用し、生産管理体制を抜本的に強化・改善するため、製造の各工程で検証を重ねながら、見直しを進めてきた。“生産管理が利益を生む”体制づくりを目指し、現在も支援を継続しながら現場改善に向き合っている。

製造部 生産管理課 課長 捧孝聡 氏
「生産管理という仕事の定義、具体的に何をすればいいのか分かったことが、よろず支援拠点に相談して良かったことの1つです。また、鈴木さんという第三者が話すからこそ、社員たちも素直に聞いてくれる部分もあると思います」(江川社長・写真右)。「鈴木さんには根気強く見守っていただいています。来ていただく度に成果報告をするのですが、回を重ねるごとに力を付けさせてもらっている実感があり、本当に感謝しています」(捧課長・写真左)。
生産管理が利益を作ると聞き製造部も問題を認識
バイオテックジャパンは約3,000種類もの優良菌株を保有する植物性乳酸菌の専門メーカー。乳酸菌を活用した発酵技術はさまざまな商品開発に応用されており、中でも米のたんぱく質を低減させた「低たんぱく食品」は業界トップシェアを誇っている。
研究開発型の企業として歩んできた同社は、生産管理の現場における課題を改善するため、よろず支援拠点に相談。2024年7月から1カ月に1回のペースで、製造業の現場改善や生産性向上等の経験が豊富なコーディネーターである鈴木裕之氏と面談を重ねながら支援を受けている。「実は昨年6月頃に製造現場でいくつかのトラブルが起き、食品メーカーとして製造部が効率的に正しく運営できているのか疑問に思ったのです。そこで別の支援でお世話になったINPIT(※)に相談したところ、よろず支援拠点を紹介していただきました」と江川社長は話す。
「バイオテックジャパンさんからの相談を受け、初めてお話をうかがったところ、生産管理を強化したい、生産管理の知識を得たいという目的がはっきりしていました。そこで私が最初にお伝えしたのが、“生産管理が製造業の利益を作る”ということ。生産管理とはそうした目的を持った仕事であると理解しましょうということでした」と鈴木氏。その言葉を聞き、「それまでの製造部は、受注が来たから作るという受身型で、稼働率を上げるという意識があまりありませんでした。鈴木さんから生産管理により効率を高めることで利益を作ると聞き、製造部もその重要性を改めて認識し始めたと思います」と江川社長。捧課長も「3〜4年前に工場長から引き継ぐ形で生産計画を作成していたのですが、生産管理とは何なのかが自分でもよく分からず、モヤモヤしていたところ、支援を通して理解を深めていきました」と話す。
※INPIT:新潟県知財総合支援窓口

支援開始当初は、コーディネーターの鈴木氏のアドバイスで、生産管理の定義を明確にするためのタートル図(製品受注から生産指示までの生産計画プロセスを整理するための図解)を作成。生産管理の役割等を図に落とし込む作業を通して、生産管理と工場の役割が明確になり、課題が整理されていった。

「捧課長もがんばっていて、相談のラリーも続くようになってきました。この一年で成長してきていると感じます」と語る江川社長。

バイオテックジャパンさんは、私が出した宿題やアドバイスをすぐに実行してくれて、スピード感があります。捧さんが自ら課題を設定し、具体的な相談が出てくるようになったのも大きな変化です。
(新潟県よろず支援拠点/コーディネーター 鈴木氏)
「生産量は最大に。生産リードタイムは最少に」が使命
生産管理面の課題解決に向けて最初に鈴木氏がアドバイスしたのは、生産管理と営業部門の協働体制を作ることだった。「生産管理の使命は、生産量を最大化すること。同時に在庫をなるべく減らし、生産リードタイムを短くすることです。そして最大生産量の情報を営業と共有し、営業は売り切るための戦略を立てる。そのための会議をしてほしいとお話ししました」。それまでも営業も参加する生産会議は行われていたが、製造部からの報告がメインだったことから新たに「製造販売会議」を開始。半年・一年先までの販売戦略について製造部と情報共有し、それをもとに生産計画を立案することで、作りすぎや欠品の防止につながり、最低限の在庫を持つように変化した。
また、製造工程の能力やリードタイムなどを落とし込んだ「生産モデル図」を作成。「受注を増やす計画があり、当初は生産量を上げるために発酵タンクを20本増やす予定でした。しかし工程間の待機日数を改めて確認したところ、思ったより長いことがわかり、ここを削ってリードタイムを短縮しました。そうするとタンクの回転率が上がり、8本増やすだけで済みました。余計な費用をかけずに生産量を増やせたのも、今回の指導があったからです」と江川社長は話す。


リードタイムを短縮したことで発酵タンクの回転率がアップし、最小限の設備投資で生産量を増やすことに成功した。

生産計画の作成に携わる捧課長は、そのコミュニケーション能力を評価され、製造部の職員を巻きこみながら現場改善を進める役割を担っている。指導を受けた内容を工場長に共有し、現場の改善が進められている。
自分たちが利益を生んでいると実感できる生産管理へ
「今後は誰もが生産計画を作成できるように、生産管理の標準化をしていくことが必要ですが、かなり近いところまできています。また、生産管理は計画と統制の2本柱で、計画を守らせる統制は人と人とのコミュニケーションが重要になります。今後は捧さんと同じように統制ができる人材の育成が必要だと思います」と鈴木氏。江川社長と捧課長もこの1年を振り返り、「自分たちが行ってきたことがベストではなく、改善の余地があったはずなのに、現場の創意工夫が少なかったということを痛感しました。鈴木さんの指導を受けて、“もっといいやり方があるはず。それを探そう”という空気が社内に生まれてきたのが、すごく大きな成果です。そして私が目指すゴールは、自分たちが利益を生んでいると実感できる生産管理をしていくこと。今はそのための理論づけをしっかり行っていきたいですし、現場一人ひとりの創意工夫が会社としての成果につながっていると感じられるような仕組みづくりを進めていきたいです」。「社長とは何年も前から現場の改善について話していたと思うのですが、私たちだけでは深掘りすることがなかなかできませんでした。今回、理想とする製造体制を実現するために鈴木さんにサポートいただき、育ててもらったと思っています」と話す。
今後は“お米から健康を”をテーマにした、高付加価値な製品の開発・製造をはじめ、ゴミ問題などの解決に向けたプラスチック分解技術、低たんぱく米を使った酒造りなど、発酵技術の可能性をさらに広げていくバイオテックジャパン。これからも検証と改善を進めながら、更なる技術活用のステージへと踏み出していく。


植物性乳酸菌の技術を活かした、たんぱく質調整ごはんをはじめとする同社の「低たんぱく食品」は、安全・安心だけでなく美味しさでも高い評価を得ている。

パックごはんの工場として日本で初めて同社は食品安全マネジメントシステム「FSSC22000」の認証を取得している。
企業情報
株式会社バイオテックジャパン
阿賀野市勝屋字横道下918-112
TEL.0250-63-1555
URL https://www.biotechjapan.co.jp/



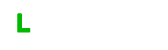
 LINEで送る
LINEで送る